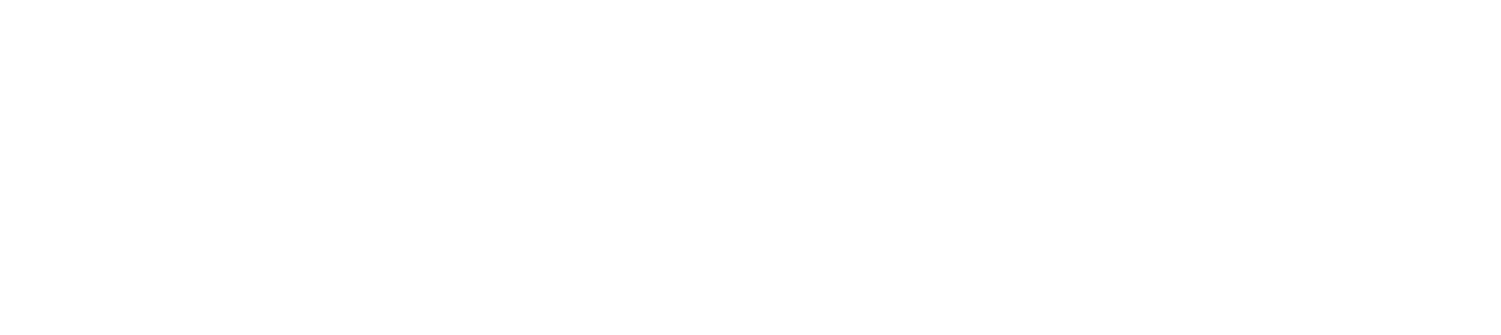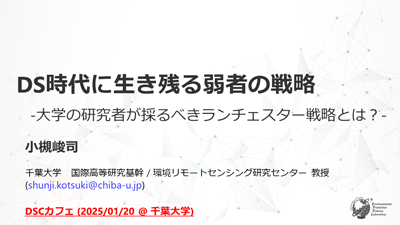第2期: 2025-2029年度 中期目標
1. 日本国内で「ここは世界一」と誇れる技術・研究を蓄積する
2. 日本・世界から、学びたい人が集まる研究室になる
3. 海外の研究者と、国際共同研究を進める (> 3件)
4.研究室から年に10本論文を生産する。かつ、Nature/Science姉妹紙に、年に1本論文を出す。
そのための戦略
1. コンピタンス first (チームで戦うチェーンを創る), followed by 国際ネットワーキング
2. Rich gets richer モデル (はずみ車) を研究で実現する
3. 留学生を含めた国際化の開始
4. teaching --> coaching
5. 原則指導の徹底。フレームワークの拡充。
第1期: 2020-2024年度 中期目標
2020年04月に策定した中期目標
1. 日本国内で「ここは日本一」と誇れる技術・研究を蓄積する
2. 日本国内で良い研究室だと認知され、学びたい人が集まる研究室になる
3. 海外の研究者から、「良い研究をしているグループ」と認知される
4.研究室から年に10本論文を生産する
自己評価 (2025年8月)
1. 日本一と誇れる技術・研究: A (定性評価)
新たにAI・気象制御に関する研究を開始し、研究所では難しい萌芽的な研究に着手した。特に、AIxDA領域では、国内でもトップクラスの研究を推進できている。JAXA共同研究についても円滑に推進し、将来的な現業プロダクト化がいくつか見えつつある。量子計算、観測位置最適化、気象の潜在空間表現など、研究室ならではの知見が蓄積した。一方で、S評価を付けるほどの卓越性は有しておらず、今後の課題である。
上手く行った理由は、研究所で行ってきたスポーツライクな研究から、大学ならではの萌芽的研究にいち早くシフトできたことが大きい。研究室立ち上げ当初は、NICAM-LETKFを中心とした全球大気データ同化システムで勝負しようと思っていたが、学部~修士の3年間が基本となる大学では、この路線で勝負するのは難しいことを、初年度に理解する。その後、「学部4年生でもサイエンスができるテーマで研究する」を徹底できていることがポイントだと思う。この点は、卒業生の大石君・齋藤匠君からの学びが大きい。このあたりの学びから、SSPなどのオフラインデータ同化と、新たに勃興してきたAI天気予報が主軸としている。
2. 人が集まる研究室: S (定量評価)
優秀な若者が集まるメンバーになってきた。特に博士後期学生の進学希望が増え、2026年4月には6人になる予定である (課程4名、社会人2名)。また、旧帝国大学など、一般に千葉大学よりもランクの高い大学からの進学を複数受けており、研究室のバリューは高まってきていると判断してよい。特に博士後期への進学学生の数は、十分に当初の想定を上回っており、S評価としてよい。上手くいった理由は、「真剣に研究している」ことが伝わっているからではないかと分析。それより「真剣に学びたい」学生が来てくれているのかと思う。また、HPや教育コンテンツの充実は、即効性はないもののと重要な活動となっている。
博士研究員も、優秀で意欲の高いメンバーが集まっている。しかし、博士研究員の多くは、人の紹介であったり公募への応募であったりで、研究室そのものの魅力で引き付けられている力はまだ弱い。学振PDや、公募が無くても問合せを受けるなどの事例が出てきており、研究室ならではの研究力・強み・魅力は、まだまだ発展可能だと思っている。
3. 国際展開: B (定性評価)
一部、研究室の研究に注目してくれている機関もあるが、総じていうとまだまだである。ただ、この点は戦略的撤退でもあった。
研究室立ち上げに苦労したため、特に修士・博士の留学生は敢えて厳しく判断した (それでも10~20件ほどは面接した)。まだ研究室としてのモラル・文化が固まっていない中で、留学生を引き受けるのは難しいと判断したのである。また正直なところ、「この研究室だからこそ研究したい」という問い合わせはそれほどなかった。研究室自体の魅力・コンピタンスが十分に育っていないことが根本的なボトルネックであり、こちらの解決が優先だと評価した。
4. 論文出版: C (定量評価)
論文生産率は要改善である。なお、国内誌・共同研究者の論文は含まず、あくまでも研究室 (Kotsuki G) 内部から出た国際誌論文出版に絞る。というのも、研究室外のパートナーの主著論文を含めてしまうと、本当の研究室の力が分からないからである。この評価方法は、東大・山崎研を参考にした。FY2020 (1件) --> FY2021 (1件) --> FY2022 (5件) --> FY2023 (5件) --> FY2024 (4件) という数字は、研究室の博士研究員の人数規模からみて、much below expectationである。
10件という数字を安定的に上げていくには、学生の論文・研究生産を高めていくことが必要になる。ということで、第二世代から、「修士を卒業するまでに、日本語でも良いから論文を1本出す」ことを、目の前の目標にした。この目標は、第五世代まで無事に継続できている (2025/08現在)。次のステップは、修士卒業までに英語論文1本、をスタンダード化していくことである (この運用は、筑波大・恩田研を参考にした)。
5. 総合評価: S
ゼロからのスタートであり、最初の5年間は業界の研究者から、「千葉大に小槻先生の研究室があり、~~で面白そうな研究をしている」という認識を得ることだった。総じて、2024年3月時点の研究室の状態は、5年前の想像を大きく超えた。特に、若くて意欲のあるメンバーが集まることで、これから何かを起こせそうな感覚は十分に持てている。このラボ・メンバーで卓越した研究成果を出せなければ、それは完全にPIに原因がある。次の5年間が勝負。
また、数値目標に現れないところでも、研究室の運営を円滑化するために時間を割いた。wikiの充実、各種学習教材・フレームワークの拡充を進め、研究推進・論文出版・研究費獲得などへのステップを刻めるように心がけた。このあたりの整備は、第2期以降に芽が出てくると期待する。
参考スライド: たまたま行った、研究室運営戦略の紹介 (2025年1月) Data Science Coreカフェにて。
研究室運営に対する考え・方針のインタビュー記事
・2025.09.16 AIが変える気象制御と天気予報 (CHIBADAI NEXT)
・2022.06.07 技術と知見を積み、世界一の研究室を創る (CHIBADAI NEXT)
補足: 評価指標と世代
S: 期待以上 (exceeds expectations)
A: 期待通り (as expected)
B: まだまだ (below expectation)
C: 要改善 (much below expectation)
第一世代 (FY2022に修士卒): 大石・大瀧・土屋世代
第二世代 (FY2023に修士卒): 藤村・齋藤・関・佐々木・河﨑世代
第三世代 (FY2024に修士卒): 島袋・毛束世代
第四世代 (FY2025に修士卒): 白石世代
第五世代 (FY2026に修士卒 予定): 井貫・宮澤世代
補足: 中期目標の達成について
こういっちゃなんだが、大学・研究センターの中期目標ほど、達成に強く拘っているわけではない。それでもなお、大まかな数値目標は必要だろうと考えている。というのも、目標を持たないとプロセスは刻めないし、普段の行動にフィードバックが掛けられないからである。例えば、第1期の中期目標については、それぞれその目標と現実の際から、「では研究室としてどのようなアクションを打つか」という形でフィードバックを掛けている。
大まかでも目標を掲げることの重要性は、例えば大学などを振り返ると良くわかる。目標以上には行けないのである。また、目標を設定することで、その偏差値レベルに到達するために、どの科目をどの程度勉強すべきか、といった形でプロセスを刻むことができる。逆に、目標を設定しないと、1年1年は信じられない速度で過ぎ去り、学びを得られない。
目標は、optimisticでよい。そこに対して、pestimisticに計画することが肝要である。目標を設定し、プロセスを刻み、観測からフィードバックをかけて修正する。その重要性は、研究室も人生も同じである。人生はデータ同化。