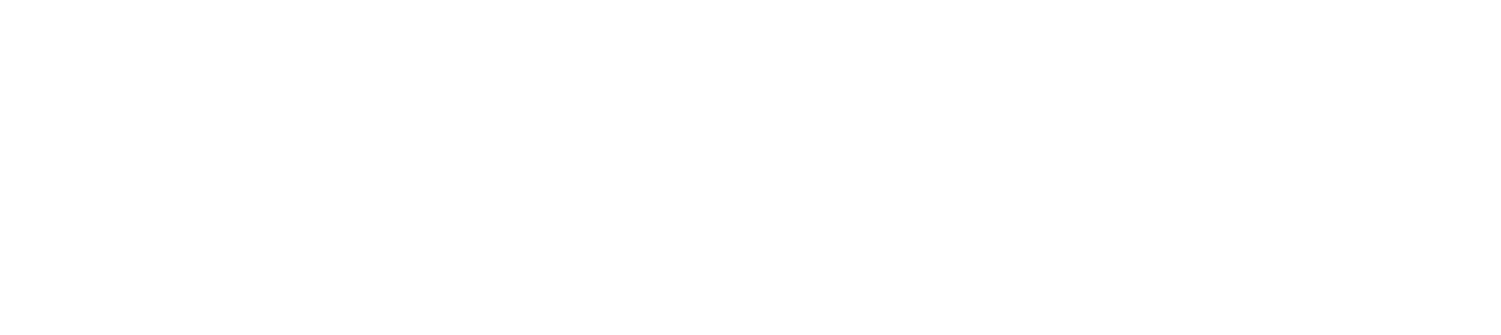何故、この記事を書こうと思ったか
大学や研究所のパーマネントポジション獲得を1つの目標にしている研究者も多いと思います。この記事を書こうと思ったのは、若い研究者と話していて、「パーマネントポジション獲得に必要だと思っている能力」と「求められている能力」にミスマッチがある様に思うことが多々あるからです。そのミスマッチとは、「論文を書けていればいればいい」という誤解が多いです。
ポジションの獲得には運が左右することも多いです。とはいえ、確率を少しでも上げることは出来ると思います。キャリアは自分自身の仮説演繹で築き上げていくものなので、以下の内容は1つの意見として聞いてください。なお、以下の記述は天才には適用されません。とはいえ、小槻自身も含め、多くの人間は、普通の人間です。
小槻自身、まだまだ経験不足で全てを知っているわけではありません。ただ、あんまり一般論を言ってもしょうがないので、「僕はこう見ています」という話を書きます。下記では、若手(~40歳)を想定します。また、企業の話は分からないので、大学の助教や准教授か、研究所のパーマネントポジションを想定します。
# シニアな先生方へ: もし、考え方が違うなと気が付く点があれば、ご指摘頂けると大変ありがたいです。小槻の考え方を正解として押し付けたいわけではなく、若者の指針にしてキャリア構築をサポートするのが目的なので。
1. 求められる能力
Tier 1: これがないと土俵に乗らない
A. 研究業績:
研究分野での重要な貢献や、ピアレビューされた研究論文の出版。博士で1-2本。博士取得以降は年1本の発表が基本ライン。国際誌への筆頭著者論文。
B. ビジョン:
5~10年の方向性として、自分が成し遂げたいことは何か。そのためにどんなキャリアを歩み、どんな研究費を獲得してきたか。今のポジションは何故選択し、どんな技術や経験を獲得したのか。
C. コミットメントと責任感:
組織やプロジェクトのミッションを理解し、自分の能力・経験で組織/プロジェクトに価値を付加できるか。「自分の研究」→「組織の価値」へ翻訳できるか。
Tier 2: 合否を分けるポテンシャル要素
D. ネットワーキング:
国内外の研究者と関係を築けるか。自らのビジョンの実現のために共同研究者を持てるか。組織が求める共同研究を完遂できるか。戦略を持ったネットワーキングを行っているか。
E. 組織・プロジェクトマネジメント:
組織/プロジェクトの研究マネジメントが出来るか。予算管理、進捗、メンバーの指導、報告書作成、学会発表ができるか。主体的に責任をTakeし、小さくてもいいので「回した経験」があるか。その経験から何を学んだのか。
F. プレゼンテーション:
研究の価値を他者に説明できるか。ほぼ、研究費の獲得能力に直結する。
Tier 3: 弱くても致命傷にはならない
G. 専門知識と経験:
研究の専門分野についての理解と研究経験。特定分野での博士号取得や、ポスドク経験など。特に研究所だと、専門性の一致性が重要。ただ、完全一致よりも拡張性が重要。専門が合っている、だけでは、採用されない。
H. 教育能力:
学生を指導する能力。授業を担える能力。着任後に伸ばしやすい (教員になる前は伸ばしにくい) 能力。
I. 言語能力 (optional) :
研究成果を英語で発表したり、国際的な研究チームと連携する能力日本の大学や研究機関では、日本語と英語の両方でのコミュニケーション能力が求められる。特に、administrativeな仕事は日本語でしかできない場合あり。
これらの内容は、ファクト・事実に基づいて判断されます。「これまではネットワーキングしてきませんでしたが、これから頑張ります」みたいな根拠のない計画 (願望) を話すのは、逆効果でしょう。また、上記の内容は、もっと普遍的な言葉で書くと、こういう力となります。
1. 独創性と研究能力 (A, G, F)
2. リーダーシップと主体性 (B, D)
3. 責任感・素直さ (C, E)
4. 協調性・マネジメント (E)
5. win-win を築ける能力 (C)
各項目の説明の前に、致命的なリスクについても先に述べておきます。この辺が危ないと判断されると、採用の可能性はガクっと減ります。
(ⅰ) 研究倫理・コンプライアンス : 一発アウト
(ⅱ) 協調性: 学内業務への対応可能性、過度に自分流に固執しないか
(ⅲ) 自立性: 指導教員や博士課程の研究テーマに過度に依存・固執していないか
(ⅳ) 教育への思想: ハラスメントへの感度、留学生・社会人への対応、どんな教育者を目指しているか
(ⅴ) トラブルリスク: 一発アウト。過去の人間関係のトラブルの噂。短期間の転職が多すぎないか。
2. 求められる能力の重要度
以上の要素は、全部必要です。そのうえで重要性は、機関によって異なります。勝手にランキングを付けます (小槻の私見です)。
S. 必須
A. 強く求める
B. 求められる
| 研究能力・実績 | リーダーシップ・主体性 | 責任感・素直さ | マネジメント | win-win力 | |
| 研究所の研究員 | S | B | A | A | A |
| 大学の付置研究所 | S | A | A | A | A |
| 大学の小講座制研究室 | S | B | A | B | A |
| 大学の大講座制研究室 | S | A | A | B | B |
どういう順に並んでいるかというと、「組織として行うミッションが、事前に定まっているか」です。研究所にはもちろんミッションがありますし、CEReS/AORI/DPRIといった付置研究所も、研究所としてのミッションが明確にあります。小講座制 (いわゆる教授・准教授・助教がいる) の研究室も、講座があるということは、その講座として一貫して教えるべき教育の責務があると、組織が考えていることになります (例えば、東大の河川研)。一方で、大講座制 (一人一人がPIになる) の独立研究室は、より一人で生きていける力が必要になってきます。
見逃されがちだけで重要なのが、「win-winを築ける能力」 だと思います。「組織のミッション」と「自分が築き上げたい世界」の両者を繋ぐwin-win なアイデアを出せることは大事だと思うし、逆にそれさえあれば、移り行く社会・組織の変化にも対応できると思います。一般論の就職活動としても、
(1) win-win: 私にはこういう強みがあり、あなたの大学/研究所の技術蓄積と合わせて、こんな新しい価値が出せます
(2) win-lose: 私はこんな研究したいです。成果を出すんで、その場所を提供してください。
(3) lose-win: あなたの組織のミッションはわかっています。本当は私もやりたいことがありますが、滅私奉公して頑張ります。
という候補者が3人いれば、(1) の候補者を選びたいと思います。ちなみに、僕は (3) を言う人は信用しません。lose-winモデルは長続きしないからです。
また、責任感・素直さはどこに行っても問われます。これには、「自分に求められている役割・ミッションをきちんと理解する力」も含まれます。やらんでいいことに責任感持たれても困るし、やってほしいことを認識されないのも困る。ただ、小槻の分析では、「研究実績」と「責任感・素直さ」はかなり相関します。おそらくそれらの背後因子は、「物事を客観的に分析できる能力」なのだと思います。
こういった能力評価で往々にしてある話ですが、これらの能力は足し算ではなく、掛け算で評価されます (重要)。研究能力が飛びぬけて高くても、どれか一つでも飛びぬけて悪いスコアがあると、採用は難しいでしょう (ただし天才は除く)。このことは、結婚をイメージすると理解できるかもしれません。どれだけ趣味が合っても、どれだけ長所が良くても、「これだけは無理」というのが1つでもあれば、長く一緒にいることは難しいんです (たぶん)。そして、パーマネントポジションの採用とは、組織にとって長く一緒に仕事するパートナーを考えるプロセスです。たぶん、長所を伸ばすのと同じくらい、飛びぬけた短所を克服することも重要になろうかと思います。
まず大学における助教の場合は、独立して研究できる能力を有しているか、が必須条件として問われます。この力は、ほぼ、研究業績で評価可能です。この時、研究業績が、ハゲタカジャーナルや、インパクトの低いジャーナル (目安として、IF < 1.5) に溢れていると、採用は控えたくなります。ポジション獲得後は、自立して研究することになるので、メンター・指導者がいる状況でも一流紙に出せないのであれば、自立してからはもっと難しいだろう、と判断します。一流紙とは、Nature/Science Seriesというよりは、業界で評価されるFull Paperです。気象であれば、JGR, MWR, QJRMSなど。水文であれば、JoH, WRR, HESSなどです。また個人的には、博士取得後の研究員時代に、新しい研究分野にも手を広げて、そこでも一流紙に論文を出せているとかなり評価が高くなります。結構、博士時代の研究をそのままずっと続ける人がいますが、それだけだと (指導教員からアサインされた) テーマが偶々良かったのか、自分の実力なのかが分からないからです (※余談1)。複数のテーマできちんと論文を出せていると、学者としての能力には大きく安心できます。
准教授以上になると、助教に求める能力に加えて、「物事を大きく動かすスケール感があるか」を見たくなります。これは、周りの人間を巻き込めるリーダーシップであったり、その研究者が掲げているビジョンの大きさ/実行可能性だったりするかと思います。また、単純に論文の数だけでなく、h-indexなどにより、インパクトの高い研究が行えているかどうかを、より見られるようになります。
下記の投稿なども参考になるかと思います。
★論文生産の目安 (ポジション獲得・JST予算)
★大学の制度や教員の仕組み
3. 能力の評価
さて、これらの能力はどのように評価されるのでしょうか。書類でしょうか。面接でしょうか。答えは、日々の活動です (※余談2)。
パーマネントポジションは、一度雇うと後戻りが出来ないので、組織も丁寧に人物調査します。例えば、10人の部局で、1人責任感が無い人が入ると、10人の仕事を9人で担うことになり、個々の負担が増えます。そのため、組織はかなり丁寧に人物Reviewをします。もし組織の構成員との面識がなければ、現在の上長へのヒアリングは確実に行われると思った方が良いでしょう。基本的に人事の鉄則は、「悪いと思わなければ採用する」ではなく、「良いと思わなければ採用しない」です (人間性に加えて、専門性などのミスマッチも含めて)。
人間性は、普段の学会活動、プロジェクトミーティング、研究室内の立ち振る舞いから、implicitに見られていると思った方が良いです。逆に言えば、責任感を持って頑張って研究に取り組んでいる若者は、いつの時代も応援してもらえると思います。博士時代の指導教員で田中賢治先生は、「頑張っている若者は、必ずどこかで誰かが見ている。だから心配しなくていい」と言っていました。その通りだと思います。
4. サーベイ
さて、これまでは一般論としての研究能力でした。そのうえで、応募しようと思ったポストが見つかったとき、どのようなサーベイを掛けるべきでしょうか。その時に大事になってくるのは、「採用する側・評価者の立場に立つこと」です。大学であれ、研究所であれば、必ず評価を受けています。例えば、付置研の場合、主な評価項目はこの辺です。
1. 国際誌論文の数。Top 10 % 論文比率や、Q1 ジャーナル率も見る。
2. 研究費の獲得
3. 特許・社会実装
しかし、すべての項目を一人の研究者が担えることは稀です。そのため、組織はポートフォリオを組んだ人事を行います (重要)。組織はどのようなポートフォリオを組むのでしょうか。
(1) 得意/不得意の多様性
プレゼン力のある研究者 (研究費獲得力)、国際ネットワーキングが得意 (top 10%論文比率などが高め)、産学連携・社会応用が得意 (特許や社会実装) 、研究の深さがある研究者 (論文数や研究費は低め、でも組織には必要)、をバランスよく採用したい。
(2) 年齢・性差・国際性の多様性
年齢はある程度バラつかせたい。というのも、国立大の多くは、「3~4年不補充」となっている。ある教員が辞めたとき、その後任を3~4年人事ができない (お金がないから)。なので、立て続けに人が辞めると困る。また、女性教員比率・若手教員比率・外国人教員比率は、文部科学省の評価ポイントになってるので、気にする。
(3) 専門性の多様性
既存の人員と丸被りする専門性を有する人は、採用しずらい。
また組織に所属するメンバーのサーベイと同様に、「(4) 組織がどのような方向を目指しているのか」も、当然調べます。基本的に、どの組織も中期計画 (5~7年の計画) を立てて、その計画に沿って組織を運営します。この中期計画は、多くの場合、HPなどで公開されているので確認することができます。
ポストに応募する30~40歳くらいになると、自分の研究能力・成果について、複数の面から見せられると思います (科学的新規性、工学的実用性、社会的インパクト、これからの若手教育に必要なスキル、など)。この複数の面から、どの面を打ち出していくか、考えていく下準備が、サーベイです。
5. 応募書類の作成
以上を踏まえて、応募書類を書いていきます。とはいえ、研究実績は履歴そのままなので、重要なのは研究計画書 (or 今後の抱負)です。
「研究計画書」は、「こんな研究したいです^^」を聞いてるのではないです。問われているのは以下の内容です。
1. ちゃんとサーベイしましたか?
2. そのサーベイに基づいて、組織を分析しましたか?
3. その分析に基づいて、win-win を提案できますか?
例えば、ポスドクの応募でも、研究計画書を作成します。僕も研究室で多くのポスドク応募への研究計画書を受け取りましたが、「私はこれまでこんな研究してきました。これからこんな研究したいです」という計画書は、その時点でアウトです。そもそも、「雇用されるんだ」という認識がない時点で、先行きが不安になります。周りの話を聞いていると、博士課程学生時代と同様に、奨学金気分で研究を続けている研究員はたくさんいるように思います。研究者は自己裁量が多い職種なので勘違いしやすいですが、学生を卒業して給料をもらうということは、会社に就職するのと同じでまずは契約の責務を全うするのがミッションだと思います。ちなみに小槻は、理研に着任して半年後の三好さんとの面談で、「学生気分は抜けましたか?」と聞かれて、ハッと気が付きました。
候補に残る計画書は、「私はこれまでこんな研究をしてきました。今回、研究室ではこのようなプロジェクトで、このような人員を募集しています。このプロジェクトでは、~の点が重要になると思います。この点で、私のこれまでのスキルで貢献できると思います (プロジェクトのサーベイ)。また、研究室では他にも~~とか~~の研究が進められています。私はそういった研究にも興味を持っており、例えば、私の~の技術を使うことで、コラボレーションを起こせます (プロジェクトを超えたサーベイ)」。研究能力の高い応募者は、ほぼ確実に後者のような研究計画書を作成してきます。
また、「今現在所属しているメンバーとの差異を明確にしつつ、協奏を起こせる可能性を見せる」ことも重要である。もし、自分と得意分野の近い教員がいるのであれば、「彼/彼女らにはできなくて、自分にはできること」は明記しないといけない (専門性が丸被りする研究者は採用しずらいから)。さらに、「今の教員とこういった連携を図り、相乗効果を出すことができる」という記述があると、「ちゃんとサーベイしてて安心だな。本当に協奏が実現するかわからんけど、こういう姿勢でいてくれるなら、きっと上手くやってくれるでしょう^^」と安心した気持ちになる。
もう一つ工夫できるとしたら、「意見を伺うことが可能な方のリスト」です。パーマネントであれば、2~3人書くのではないでしょうか。
まずは博士の指導教員や、現在の上長 (1~2人)。書かれていないと、危険な香りがする。というのも、普通は書くから。なのに書かれていないとすると、「もしかして、過去の指導教員や、上長と、上手くいってなかったのかな?」と邪推する。
もう1人書けるとしたら、「自分の知り合いで、かつ、人事委員会に入るであろう教員の知り合い」を書きたい。というのも、採用する側としたら、「この~さんて方について知りたいんだけど、、、」となる。その時に、委員会メンバーの知り合いがこのリストに含まれていれば、「私、この先生を知っているので、聞いてみますよ」となる。まぁ、言われてみれば当たり前の工夫ですよね。
ちなみに、小槻が千葉大に応募した時のサーベイはこの辺りである。
1. JAXAの衛星プロジェクトのアルゴリズム開発の中心を担う堅実な研究者より、独立して研究できる研究者が必要、と読んだ。一つはCEReSはPIがそれぞれ研究者であったことと、直近の全国共同利用・共同研究拠点評価で、科研費の獲得の低さの指摘を受けていたから。なので、JAXAの予算を取れる能力よりも、科研費獲得能力が問われると読んだ。
2. 衛星よりも計算科学能力が重宝される、と読んだ。これも、直近の全国共同利用・共同研究拠点評価で、「衛星を超えた分野の発展が限定的である」みたいな記述があったから。なので、「衛星科学研究に強味を持ちます」よりも、敢えて「衛星データはInputとして利用して、大規模計算でこんな付加価値を出せます」という提案書に振った。また、そのような時代的背景を加え、どうしてそのような研究が必要かを書いた。
3. コミュニティを広げられる能力、社会実装にも展開できる能力が必要、と読んだ。これは、当時のメンバーが理学に偏っており、社会実装方面の能力が欲しいのではないか、と考えたから。当然、所属している教員と起こせるコラボの可能性は書いた。また、全国共同利用・共同研究をどう発展させられるか、書いた。
以上のサーベイを踏まえ、「今後の研究計画」 の最初の0.5p は、この様になった。参考まで。
科学哲学の根源的な問いは、「我々は世界について知ることが出来るか否か」である。経験科学において、人類の知の拡大は仮説演繹法によって果たされてきた。それは地球科学においても同様であり、観測データに基づく法則発見(帰納)、法則に基づく予言(演繹)、予言検証が重ねられ、巨大な知の巨人が形成されてきた。現代においては、コンピューティング技術の進展に伴い、物理法則に基づく数値シミュレーションが第三の科学的手法として一般化している。更に近年は、観測ビッグデータの拡充と深層学習・AI研究の発展により、データ科学が第四の科学的手法として台頭してきた。大きな潮流として、シミュレーション科学・データ科学を統合による、地球環境予測の高度化が望まれる。
データ同化は、物理モデルと観測データを最適につなぐ、統計数理や力学系理論に基づいた学際的科学である。特に数値天気予報においては根本的な役割を果たしており、大気の観測データを同化する天気予報技術は高度に発展してきた。応募者はこれまで、特に地球システムのモデリング研究とデータ同化数理研究において、基盤技術開発と卓越した研究実績を重ねてきた。研究の更なる発展のため、地球環境リモートセンシング研究の拠点である千葉大学・環境リモートセンシング研究センター(CEReS)において、CEReSの有する人的・物的・データ資源との相乗効果を図りたい。環境リモートセンシングとデータ同化研究の融合による地球環境データ同化研究の発展を目標に定め、(1) 最先端科学研究によるコアコンピタンスの確立、(2) センター内外の研究者との協奏、(3)地球環境予測と教育を通じた社会貢献、を3本の矢として研究・教育活動を推進する。地球環境データ同化研究の深化を通じて、CEReSのミッションである「リモートセンシング情報統合」「衛星利用の高度化」「人材育成」に、それぞれ下記の計画で貢献する。
(以下略)
6年ぶりに読み返してみて、自分でも良いなと思うのは、「CEReSの有する人的・物的・データ資源との相乗効果を図りたい」という姿勢である。「自分の目標・ビジョンがあり、そのビジョンの実現のためには、あなたの場所が最適なんです」と言われると、この人はバリュー出せそうだし、かつ、長く貢献してくれそう、と思う気がします。
最初の科学哲学の話は、良かったのかは分からない。個人的な意図は、「まず手にとめて読んでもらう必要がある」と思ったから。一般論として、大学のパーマネントポストは、20~30人の応募になることもザラである。その中から、まず自分の提案書を読んでもらうには、ファーストインプレッションを出す必要があるのでは、というのが当時の仮説である。公募に限らず提案書は、「失点しないこと」よりも、「得点を取りに行くこと」の方が重要になる。無難に計画書をまとめても、ほかに意欲的な計画書が並んでいれば、読んでもらえない。書いた本人の熱量が、計画書には滲んでいるものである。(たぶん、AIにこの熱量は出せない)
なお、どれだけ頑張って書類を書いても、無理な時は無理である。それは、公募要領という表に出ない組織のロジックがあり得るからである。能力が十分に高くても、求められている人物像とミスマッチがあれば、それはもうしょうがない。でも、応募しないと、そもそも可能性は0である。また、現在の大学教員人事は、部局には最終人事権が無く、大学本部が最終決定権を握っていることが多いように思う。なので、大学本部の意向も関係してくる。
6. 面接の準備
面接に読んでいただいた時点で、候補者は2~3名まで絞られていると思ってよいと思います。なので、ここでもうひと踏ん張り。
基本的には、応募書類と同じで、サーベイに基づいてプレゼン資料を作成する。プレゼンは、自分の話したい話をするのではなく、相手が欲しい情報を提供するのが目的である。どこまでやりこむかは人それぞれだが、小槻は人物サーベイを行った。具体的には、当時の研究センターの教授のHP、論文リスト、個人ブログなどを読んで、どのような思考を持っている人がいるかをサーベイした (プレゼンの現場にいると思ったから)。
1. 大前提として、国際誌への論文出版力は必要条件
2. そのうえで、論文だけでなく、社会の問題を解決する研究が必要
3. あまりプレスリリースなどを目的化するのではなく、科学者として誠実に活動する
4. 独立研究室を持つ意欲と、それに向けてどのような準備・経験を行ってきたか
面接では、教育研究能力だけではなく、人物評価もされる。だから、ある程度相手の価値観は知っておかないといけない。個人的に参考になったのは、学会などへの寄稿の記事である。ここには、論文よりも、研究者・教育者としての価値観・哲学が出ていることが多い。
余談ではあるが、小槻の場合はラッキーなことに、CEReSの市井先生が小槻のことを覚えていてくれた。2019年の着任に対して、市井先生にお会いしたのはまだ博士学生時代だった2013年5月の韓国の国際会議HESSSだけである。その時に、どうもお昼ご飯をご一緒したのだが、その時の印象がとても良かったらしい (市井先生の研究の話を根掘り葉掘り聞いてたらしい。小槻はあんまり覚えていない)。
結局、何が縁になるか分からないのである。ポストを獲得しようと思って、その時から動き始めたのではたぶん遅い。動き始めるのは、これを読んでいる今からである。学会やプロジェクトのアクティビティなど、主体的に活動していれば、必ず注目される。主体的に活動すれば、当然、責任や仕事は増える。それもまた、自分自身を成長させるのである。一方、受け身でいても、人の認知は受けられない。
時々感じる誤解
1. 守破離: いきなり、自分のオリジナリティを求めすぎている。それよりも、今与えられたポジションで自分のミッションを全うし(守)、その中で自分のオリジナリティを出し(破)、新しい研究に昇華させていった方が良い(離)。パーマネントポジションとはいえ、「あなたがやりたい事をなんでもやって良いですよ」なんて場所なんてない。繰り返す通り、大学であれ研究所であれ、組織にはミッションがある。そのミッションを読み取り、自分のやりたい事とのWin-Winを築けないといけない。
2. ポジションをとってからやる: 例えば、研究マネジメントや後輩の指導などは、ポスドクの仕事ではないと思うかもしれない。だけど、この辺の業務をきちんと回せる力は、パーマネントポジションの獲得に必須です。「ポジションに着いたら頑張ります」で、納得してくれる人はいない。ポジションが上がると、研究員の時代よりも責任が増え、自分自身に使える時間は減る。研究員の時に出来ないことが、ポジションを取って出来るとは思えない。
3. 自分の研究に専念したい: 気持ちは分かる。けど、多くの凡人にとって、一人で出来ることなんて限られているし、視野狭窄に陥ってどんどんとニッチな研究に落ちて行ってしまう。自分のオリジナリティを持ちつつ、周りを巻き込んで大きくしていく姿勢は見たいもの。結構、研究にこだわりが強い人が、この視野狭窄型が多い。
4. 論文を書いていればいい: そんな訳ない。求められる能力の中で、技術力・科学力は必要条件の1部でしかない。とはいえ、論文を書いていないと、そもそも候補に上がらない。またプロジェクトで雇用されていても、そのプロジェクトのコアに踏み込んでこない (ひどいと博士時代の研究を継続して論文を書く) 場合が見られる。カンファタブルゾーンに留まり、新しい研究にチャレンジできないのではないか、と見えてしまう。
5. 学会・プロジェクト会合の発表の軽視: ある人間の評判は、その人間の行動の積み重ねである。それぞれの機会でベストを尽くさない人間に、チャンスは回ってこない。誰だって、頑張ってる人を応援したい。あと、聴衆を置いてけぼりにする発表を繰り返すのは、非常に印象が悪い。
繰り返しになるが、パーマネントポジションの獲得に向けた活動は、日々の研究活動から始まっているのである。
これまでに頂いた他の先生方からのフィードバック。
既にポジションを獲得した方から「この記事を見ました」というコメントを得るんですが、一番共感を得るのは、「守破離」のところでした。下記、いただいたコメントを参考までに掲載。
1. 守破離は非常に大事だと思う。自分自身は、守の前に離れようとして、キャリアで苦労した。オリジナリティを、人と違う (人がしていない) 研究をすることだと思い込んでいた。ただ、基本的に現代では、誰もしていない研究は、インパクトが低い研究であることが多い。自分のオリジナリティを、研究の深さ出そうと思うことが重要だと、キャリアを振り返って思った。
2. 「組織のミッション」と「自分が築き上げたい世界」の両者を繋ぐwin-win なアイデアを出せることは、ポジションを獲得するうえで非常に大事だと、思う。逆にそれさえあれば、移り行く社会・組織の変化にも対応できるし、研究のアイデアを出せる力は、このwin-wint提案力と大きく関係していると思う。この辺の柔軟さは、外部資金の獲得にも通じる。「自分が好奇心でやりたいです!」というテーマに、それだけの理由で出資してくれるfunderは、基本的にいない。「社会・学術・会社において求められていること」と「自分が進めたい研究」の両者を繋ぐ提案をしていく必要がある。
3. とある教授より。准教授であれば論文20本、教授であれば50本が1つの目安だったが、最近は出版論文数も増えてきているので、この目安は増えつつあるように思う。採用は大きく、(1) 研究成果 と (2) 人間性・協調性 を見る。(2) は面接ではわからないので、推薦者や周りの方の評判は丁寧にサーベイしないといけない。20, 30人を超えるような組織になってくると、協調性が低くてもとびぬけて研究できる人を採用できるかもしれない。が、20人以下の部局であれば協調性は必須だろう。また、准教授以上は、「将来的にこの人は教授になれるか」を見る。35-40歳であれば、成果を挙げつつ、周りを巻き込んで大きなことを起こせそうな、兆しは見えるものである。
4. とある教授より。博士取得後に研究テーマをどれくらい拡げられたか/変えられたかを見る。それが学者としての力を見る試金石になるから。博士研究のテーマを、そのまま長く続けている研究者は多い。しかし、多くの場合、組織には組織のミッションがある。そのミッションに沿った研究をしてほしいと思っている。そう考えると、1つの研究テーマを継続して見える研究者は、scientistとしては優秀かもしれないが、大学教員としての受け入れは難しい。
面接でよく聞かれていること
いろんな面接に同席していると、同じようなことが何回も聞かれる。
1. 「この2年間は論文が出てないけど、何があったんですか?」: まず、活躍している研究者は、最低でも年に1本は論文を書いて当然と思っている。丸2年、第一著者の論文が出ていないと確実に突っ込まれる。なお、もちろん英語論文です。育休や民間就職などの理由があれば、問題ない。
2. 「具体的に何するんですか?」: science以外の観点で、組織とどう協調していくか (future plan) をスライドに含めていることは多い。でも、それがただの願い (hope) になっていて、actionable な 計画 (plan) になっていることが多い。そういったことを洗い出すために、こういう質問はよく出る。
3. 「将来の計画ではなく、過去のハードファクトを話してください」: これも多い。そもそも、「これからこんなことをやります」って話が多すぎる候補者は信用できない。信用できる候補者は、過去の実績・ファクトに基づいて話す。
余談1: 博士時代の研究の継続
これ自体が問題な訳ではないのだが、「自分のComfortable Zoneに留まり続けたい人なのかな」と思われてしまうことが、リスクです。
世の中から求められる役割や研究内容は、社会・技術・予算の関係で常に変動を続けます。その変動に対して、フレキシブルに適応を続けられるか、というのが見たいポイントです。また、助教-->准教授-->教授としてステップアップしていく中で、求められる役割も変わってきます。どこかで必ず、「プレイヤーの研究者としての成功体験」を捨てて、「人・グループを育てながら成果を上げていく」フェーズに移行していく必要があります。
逆に成長意欲がある人は、逆に自分からComfortable Zoneから脱却していきます。Comfortable Zoneに留まっていても、自分自身が研究者として/人間として成長できないからです。そういう成長意欲がある人は、自立した研究者としても、十分にやっていけるだろうと思うわけです。その一つの表れが、「博士取得の後に、別の研究テーマでも研究成果を上げて論文を書いていけるか」なわけです。(逆にキャリアが若いと、それくらいしかComfortable Zoneに固執するかどうかを見る手段がない)
余談2: 日々の活動について
繰り返し書いているように、パーマネントポジションの獲得に向けた活動は、日々の研究活動から始まっています。雇用する側も、いつポストが空くかは分からないものの、いざその時になって困らないように、普段から学会・プロジェクトなどで、アクティブな若者はチェックしています。「あの子、普段はどうなんですか?」という話は、普段からシニア世代でします。僕も聞くし、相手から聞かれることも多々あります。下記、具体的にあった会話の例です。
彼/彼女は、研究能力はずば抜けて高いが、研究室の運営にはサポーティブではない。結果的に、教授を始めとする他のスタッフの負担が高くなっている。
彼/彼女の研究は、博士学生時代は何やってたんですか? --> 全然違う分野なんですね。その中で、研究を着実に進めて、きちんと成果を上げてるのは素晴らしいですね。
ということで、「彼/彼女はどうですか?」という話は、普段から交わされております。ジョブのミスマッチを防ぎたいのと、やっぱり良い人を採用したいからですね。逆に言えば、誠実に頑張っていれば、誰かは必ず見ているので、心配はいらないです。