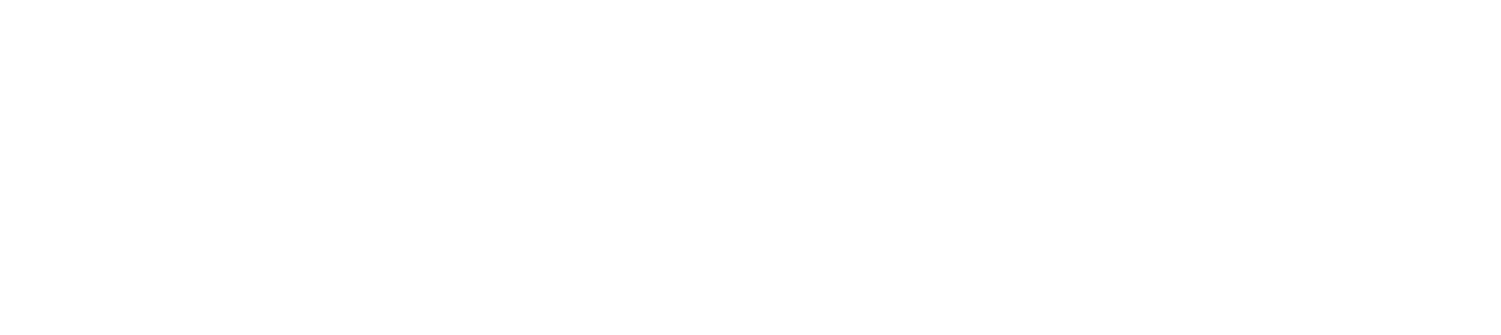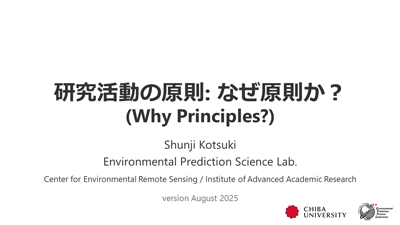2025年度から研究室では、「原則による指導」を掲げて取り組みを始めています。即効的な「答え」を教える状況指導と異なり、 普遍的な「考え方」を教えるのが原則指導となります。
この原則指導を掲げた理由は、主に2つあります。1つ目の理由は、10年後が全く見通せないVUCA時代に生きているという実感です。不確実性の高い時代を生き抜くためには、出口の近いスキルや知識よりも、深層のファンダメンタル・原則がより重要になります。そのファンダメンタル・原則を伝えたいというのが1つ目の理由です。
2つ目の理由は、研究室の責務として次世代のリーダーを輩出するためです。小槻の意見として、次世代のリーダーとは、「本当の自由」を獲得した人間だと定義します。ここでいう「本当の自由」とは、(1) 自分の人生の意味を考え抜いて、人生の目的を定めて (※余談1、余談2)、(2) そのために自分は何をすべきか、目的への道を理解し、(3) 目的を実現する力 (道を歩く力) を有している状態 を指します。このうち、目的を実現する力の獲得を支援するのが原則による指導です。
原則による指導の実現は、指導者にとっても苦痛です。普段の教育研究を1つメタ・抽象的な視点から考え、その構造を捉える必要があります。ただ、長い目で見たときに、この「原則による指導」は正しい方向であるとも確信しており、時間をかけてでも整備していきたいと思っています。
Part 1. 原則による指導とは何か、なぜ原則による指導なのか
Part 2. コミュニケーションの原則
Part 3. Critical and Structural Thinking の原則 (作成中)
余談1: 人生の目的
これを見つけるのは、そんなに急ぐ必要はなく、40歳までに色んな経験をしながら見つけていけば良いと思います。小槻自身も「これが自分が生まれてきた目的なのかもしれない」というのがぼんやりにでも腑に落ちたのは、30代後半でした。立花隆さんの「青春漂流」という本にいい言葉があるので、引用します。
青春とは過ぎ去った時に初めて、あれが青春だったのだと気が付く。じぶんの生き方に対する迷いから吹っ切れた時に、青春が終わる。自分の生き方を模索している間は青春なのだ。青春中は、自分に忠実に、大胆に生きようと思うほど、恥も失敗も多くなる。青春とは、謎の空白時代である。情熱をかけるべき対象を追い求める時期である。自分の人生を賭けられるようになるまでは、それにふさわしい自分を創るために、自分を鍛えぬくプロセスが必要。そこに必要なのは、なにものかを求めんとする意志である。
余談2: 人間は自由の刑に処せられている
哲学者、ジャン=ポール・サルトルの言葉です。サルトルによると人間というのは、過去の自分から脱出して新しい自分となっていく存在であり、世界への関わり方を自ら選択して、自分自身をつくっていく存在であるとしている。サルトルはこのことを自由と呼ぶ。だが人間は自由であるということをやめることはできず、このことを人間は自由の刑に処されているとしました (wikipediaからの引用)。
以下は小槻の解釈です。現代はロマン主義の時代で、とかく「あなたの人生の目的は何ですか?」を問われます。この「人生には意味があって然るべき」という価値観は決して普遍的ではなく、現代の一過性の価値観です。とはいえ、私たちは今を生きており、それなりにこの価値観に縛られています。ここで
・自分の人生の目的を定義し、そのために生きなければならない。
・そのための時間も自由も十分にある。
・だけど、その目的が分からず、初手に何をすればいいか分からない (焦燥感・劣等感)。
という状態に、20代の頃はなりがちだと思います (小槻はそうでした)。これが小槻なりに思う、現代における「自由の刑」であり、冒頭で言っていたのは「この状態 (時間も自由もあるが目的が分からない)は、本当の自由なの?」ということでした。
技術としてファンダメンタルを身に着けつつ、青春時代の一番の宿題は、「自分の人生の目的」を定義することだと思います。これにもいくつかパターンがあるように思うので、また時間を見つけて筆を執ります。